北の注目される役者たち >> 小林なるみさんインタビュー
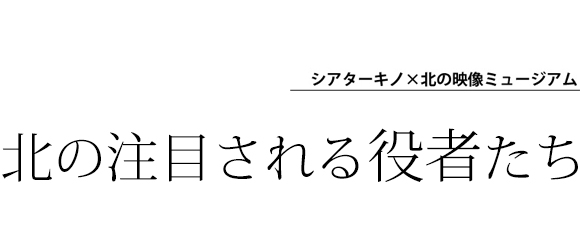
小林なるみさんインタビュー

北海道ゆかりの役者を応援するインタビュー企画。第一回目は、札幌の小林なるみさんが登場。「劇団回帰線」に所属する舞台俳優として活躍する一方、2014年の「そこのみにて光輝く」、2015年6月公開の「きみはいい子」と、呉美保監督の北海道ロケ映画にたて続けに出演。前者は「スナックのママ」、後者は「学校の先生」という対照的な役どころを見事に演じた。舞台に、映像に。多彩な表現に挑む彼女のこれまでとこれからを聞く。(※インタビューでは、作品の内容に触れる部分がございます。ご注意ください)
text:新目七恵
監督の〝愛〟を感じた「そこのみにて光輝く」
―素敵なお着物姿でお越しいただきありがとうございます! さっそくですが、まずは映画のお話から。「そこのみにて光輝く」出演の経緯をお教えください。
市民オーディションなんです。知り合いのフェイスブックの投稿で知り、「ほぅ」と思いまして。原作者である佐藤泰志さんの著書をできるだけ読み、呉監督さんの過去の2作品(「酒井家のしあわせ」「オカンの嫁入り」)を拝見した時に、「出たい!」と猛烈に思いました。オーディション対象は函館市民でしたが、「いや、道民として行こう!」と勝手に拡大解釈して(笑)。とにかく監督さんにお会いしたくて、足を運びました。
―商業映画のオーディションは初めてですか。
実は以前、ナレーションの事務所に入っていたので、ラジオ番組やテレビCMなんかには出たことがあるんです。…が、若い頃、「映像」って自分に向いてないな、と思っていて。
―えっ、なぜでしょう。
舞台出身なので、どうも質感が違うといいますか…。20~30代の頃だったので、演技の方法論をひとつしか知らなかったせいもあるんでしょうね。周りの反応が良くないな、と感じていたんです。だから、私は舞台向きなんだ、と思いつつ、いただいたお仕事をこなしていたんですね。

―ではなぜ今回、積極的にオーディションをお受けに。
実はオーディションの3か月前、のどの手術をしたんです。それまで5年間ほど、ほぼ休みなく働いていたんですが、病気を機に、「もっとやりたいこと。食わず嫌いだったことにもチャンスがあればやってみよう」と思って、仕事を半分くらいに減らした時期でした。
―なるほど。
監督の作品を見た時に、人間の描き方が本当に温かくて…特に女性の描き方が、きれいすぎず、汚すぎず、ちゃんと人となりで描いていることに感銘を受けて、「映像」が得意不得意は問題でなく、どうせダメなんだから行ってみようという前向きな気持ちになったんです。仕事を減らしたので時間的な余裕もあり、函館に行けました。
―では、ちょうどタイミングが合ったんですね。
「(病気は)このためだったんだ!」と勝手に受け止めました(笑)。色々あったので、逆に怖いものがないというか、失うものがないと言いますか…なんだか恥ずかしいですね(笑)
―いえいえ。良い意味で、肩の力が抜けていたわけですね。
しかも、術後で声が完全に回復していなくて、低いし大きな声が出なかったんです。それをオーディションで伝えたら、「映画だか大丈夫ですよ」と言われて受けさせていただきました。
―手応えは。
これが、思うようにのびのびできたんです!(笑)
―良かったですね! 初めてお会いした呉監の印象は。
頷きながら見てくれたことを覚えています。とにかく、自分が悔いなくできたこと、病気の後もちゃんと表現できるんだ、ということに満足しました。だから結果にはこだわっていなくて…。
―そこに合格の連絡がきて。
ビックリ! オーディションでは、「スナックのママ」と、高橋和也さん演じる中島の「妻」のセリフを読んでいて、何となく「妻」役かな…と思っていたら「ママ」だったので、それも意外でした。でも、「やります!」と即答しました。
―本番までのご心境は。
台本をいただいて、出演シーンは2つでしたけれど、非常に重要な場面だったので、「これは大変だ!」と。ありがたいような、嬉しいような気持ちの反面、「どうしたらいいんだろう」という困惑も沸いて、複雑な心境でした。でも、あのオーディションの演技で選ばれたのだから、そのままいっちゃえ!と臨みました。
―そうして、いざ本番に。
当日、ロケ地に集合だったんですね。撮影場所は、函館市内の実際のスナック。シーンを一度通した後、カメラワークの打ち合わせの待ち時間に、呉監督に「このママって、二人(綾野剛さん演じる「達夫」と池脇千鶴さん演じる「千夏」)の仲に対して、否定でも肯定でもなくていいんですよね」と質問したんです。「ただそこにあるものを見つめて、受け入れるというか、そういうことですね」と。すると、「まぁ、このママも色々あったんだろうね~色々見てきたからかなぁ」とポツポツおっしゃってくれて…。それは、私の言ったことを肯定してくれてるなと感じたので、そのまま演じました。

(C)2014佐藤泰志/「そこのみにて光輝く」製作委員会
―本番中に、ちょっとしたアクシデントがあったとか。
そうなんです! 池脇さんが綾野さんに近づき、平手打ちするシーンの時です。バランスを崩した綾野さんの手がビール瓶に当たって、倒れた瓶が灰皿の上でシーソーみたいに揺れてしまったんです。綾野さんが出て行った後、私がフレームインしてセリフを言わなければならなくて…。
―印象的なセリフでしたね。
『女の顔して』。…ということは、池脇さんの顔を見なきゃいけないんです。カメラの外側でパニックになりつつ、早くフレームインするとお二人の芝居が壊れるし、どうしよう…と思ってキョロキョロしたら、スナックで実際に使っていた布巾を発見。その勢いでボンッと投げて、拭いている体でセリフを続けたら、そのテイクが採用されました。
―劇中では何の違和感もない流れでしたが、その瞬間は焦ったでしょうね。
自分としては必死でしたけれど、結局それが採用されたのを試写会で知り、私の中で勝手に監督からの「愛」を感じて…。実は、あのシーンを観ただけで泣きました。
―そうですか!
なんというか、今まで色々積み上げてきたものを、すべて肯定してくれた気がしたんです。苦手だと思っていた「映像」にきちんと出させてもらい、東京の俳優さんと同じように扱っていただき、心のいいスタッフさんたちとお仕事できて…。もう、これが最後の作品になってもいいな、と思うくらい本当に嬉しかったです(笑)。続けていると〝ご褒美〟ってあるんだな、またいただいちゃったな、と思いました。

―現場での呉監督はどんな雰囲気ですか。
俳優とマンツーマンで淡々と話していていましたね。たとえば、池脇さんへの演出も、カウンターを挟んだ私の耳には聞こえないほどのやりとり。でもその後、必ず彼女の演技が変わるんです。映像の現場では初めて会うような、爽やかさというか、器の大きさを感じました。って、年下の方ですけど(笑)。
―凄いですね
ある時、撮影スタッフの女性の方たちが、移動で軽やかに歩いている監督を見て、「なんかかわいいよねー」とふと漏らすのを聞き、いい雰囲気の現場だなぁとも思いました。
―照明とカメラマンのスタッフは「海炭市叙景」と同じ方なので、存じています。
カメラマンの近藤龍人さんにも救われました! 綾野さんにビールを出すシーンの後、私は店の奥のドアを開けて一度引っ込むんですね。実はその先は半畳ほどの物置。その後、池脇さんもドアを開けるんですが、その時、待機中の私が映り込んでしまって、やり直しになってしまったんです。
―うわぁ、それは大変でしたね!
「またかよー(怒)」なんて舌打ちされても仕方ない出来事で、「すみません!」て慌てて謝ったら、近藤さんが「僕がカメラの位置を伝えなくてごめんね」と逆に謝ってくださって…優しかったです。現場全体がそんな温かい雰囲気に包まれていて、それがどのシーンにも溢れている気がします。なんて素敵な映画に出られたんだろうと、ありがたい気持ちで一杯です。

―2015年1月には、キノでアンコール上映され、小林さんがトークされました。ご覧になった方からの反応はいかがですか。
久しく会ってなかった知り合いが駆けつけて下さって嬉しかったです。あと、知り合いの役者が、「なんだ、このスナックのママ、どこの女優さんだ?」と思ったら、エンドロールで私の名前を見つけて驚いていました(笑)。上映後、握手を求められて、思わずガッツポーズ!みたいな(笑)。

―それは嬉しい出来事でしたね。
芝居は一度きり、その場限りですけれど、映画の場合、各地の映画館やDVDなど様々な場所で観ることができます。その意味で、いろいろな人に「まだ続けているよ」を伝えられるソースになったかな、とも感じました。
じわーっと湯たんぽのように温まる「きみはいい子」
―「きみはいい子」では、主演の高良健吾さん演じる「岡野先生」の同僚、「正田先生」を演じられました。
今回もオーディションを通して出演が決まり、今度はロケ地の小樽に通いました。ロケ場所が坂の上にある小学校で、休日を利用して土日を中心に撮影したので、3、4回足を運んで。実は私の出演シーンからクランクインしたので、初日のピリピリした緊張感の中、セリフを言ったのを覚えています。

―映画のキーとなるセリフもある役どころ。役作りなどで苦労された点は。
前回より役のイメージを作っていったんですね。キャリアウーマンぽい先生の感じで。すると、「普段通りでいいから」と言われてちょっと悩みました。でもさらに、「ほらいるじゃない、こんなおばさん。チャキチャキして普段は気さくなのに、先輩後輩の線をパッと引くような鋭さもあって、でも仕事は任せておけば大丈夫みたいな。〝おばちゃん〟ぽい先生」とアドバイスをいただき。それで、少し足を開いて歩いたり、動きもわざと乱暴にしてみたりしました。
―なるほど。
「そこにみて光輝く」は半日だけの参加でしたが、今回は1週間ごとにワンシーンずつの撮影。なので、日にちが経つとちょっと忘れちゃうんですよね(笑)。そうした中、ずっと現場入りしている主演の高良さんは、会うたび、どんどん顔が違って見えるんですよ。

(C)2015 アークエンタテインメント
―へぇ!
後半なんか、本当に「先生」に見える瞬間もあり、なんだか羨ましい反面、自分は大丈夫かな…と確認しながらの作業でした。もちろんロケは楽しかったんですけれど、そういう面では前回より大変でした。
―小樽の試写会で、高良さんが「生徒役の子どもたちが僕を先生にしてくれた」とお話しされていましたが、実際にその様子を目の当たりにされたのですね。

そうですね。たとえば後半、特殊学級の先生役で、劇団回帰線の仲間・松岡春奈が登場するんです。彼女が「花咲か爺さん」のお芝居を、実際に障がいのある子どもたちの前で演じるシーンがクライマックスにつながるのですが…
―心に残る場面でした。
映画ではわりと短いシーンですけれど、実際はお話を全部演じたので2時間くらいかかっているんです。廊下でスタンバイしていた私は、教室の空気がうねるのを感じて、「すごいシーンだな」と感心していました。もちろん高良さんもその場で聞いていて、その後、衣装替えのため、お互いついたてを隔てて準備している時に、「あの子たち頑張ってたけどさ、うちのクラスの子たちも頑張ってますよね?」とスタッフさんに話していたのが聞こえて(笑)。そんな高良さんの〝先生ぶり〟も微笑ましかったです。着替えを終えた私にも「そうですよね!」と確認するので、相槌を打ちつつ、劇団の後輩のことを心の中でそっと褒めました(笑)。
―(笑)可笑しいですね!
柔軟な方なんですね。気さくな方で、ロケ中も話しかけてきてくれて。
―映画の冒頭から、やりとりがありますね。
あのシーンの撮影時には、あの立ち位置で待機中、突然高良さんが「今度丸一日撮休のとき、日帰りで知床まで行けますか?」なんて聞いてきて(笑)。「一日じゃ行けないよ~!」と答えたら、「バスとかJRとか使ったらどうでしょう…」なんて続けるので、セリフ忘れちゃう…って内心焦りつつ会話したのを覚えています。
―役にどっぷり入り込むタイプではないのですね。

あそこは動きのタイミングもあってシビアなシーンだったんですが、普通に話していて、面白い方でした。切り替えるのが上手なんだと思います。
―高橋和也さん演じる「大宮先生」とのやりとりがあった、コピー室のシーンも印象的でした。
「そこのみにて光輝く」同様、脚本は高田亮さん。彼の台本を読んで気付いたのは、決めゼリフがないんですね。
―決めゼリフ。
奇をてらったセリフというか、流行語になるような言葉がないという意味です。けれど、色々な言葉が積み重なった時に、その人が見える、じわっとくるようなシナリオの書き方をされている気がします。内田樹氏の著書「もう一度村上春樹にご用事」の中で音だけではなく文章にもあるという「倍音」の効果についての説明で「シンプルに、ストレートに、ただそこにあるものを「それ」と指示し、記述するだけの機能しか託されていないようなセンテンスからのみ「倍音」は生成する。仰々しい舞台装置や美辞麗句の伽藍の上に「ごお~ん」と鳴り出すわけではない。」という文章があって、これがとても近い感じです。
―なるほど。
コピー室のシーンも、何気ない会話のやりとりから、あそこで「ここの職員室はちゃんと空気が通っているな、わりといい学校じゃん」と思えました。わずかなシーンですが、それぞれの個性や人間関係が浮き彫りになるシーンだと思います。
―確かに、他愛のない会話が、振り返ると胸に残っています。
普段見落としがちな日常会話の積み重ねの仕方が、何て素敵なんだろう!…と、感動して読んでいました。試写会の時、実は映画の中盤、高良さんが甥っ子にギュッとされた瞬間から、もう泣けてしまって…。

―同感です。あのシーンの、息づかいが伝わる音も良かったですね。
呉監督の作品には、五感を刺激されるんです。「そこのみにて光輝く」は「匂い」を感じましたが、この「きみはいい子」の場合は「温度」かな。体がじわじわ温かくなるような映画でした。
―なるほど
重たい題材を扱っていますけれど、大事件が起きるとか、すごい悪者が出てくるわけではない。けれど、ひとつひとつの何気ないシーンが積み重なることで、こんなに明日頑張ろう!と思えるんですねぇ。監督もおっしゃっていましたけれど、誰かの人生を大きく変えることはできないかもしれないけれど、誰かが見ていたり、ふと手を差し伸べてくれたりすることで、今日の嫌なことだけでも救われるんだなぁ、と。何だか、じわーっと湯たんぽみたいな映画で、見終わった後、すぐに「もう一回観たい!」と思いました(笑)。
―初見から内容に入り込んで楽しめたんですね。
出演シーンがわりと前半だったのも影響しているかもしれません。でも最後に劇団の後輩が登場して、泣き笑いになりましたけれど(笑)
―劇団回帰線ファンも見応えがある映画になりましたね!
ええ。皆さん、最後まで見逃さずにいてください(笑)
壊し、壊され。〝七変化〟の役者を目指して
―そもそも、役者としての原点は、小学校の時に演じた人形劇「赤ずきんちゃん」だったそうですね。
そうなんです。誰もやりたがらない「オオカミ」を担当して、ちょっとしたアドリブの動きをしたら褒められて、それが嬉しかったんです。
―中学、高校も演劇部に入って。
高校演劇部の同期に、プロを目指すアツい子がいて、私も影響されてオーディションを受けたりしてました。非常に楽しかったです。
―ところがその後、演劇の道はご両親に反対され、就職を決めた高校3年の時、地元・江別の劇団「川」に入団されます。
好きなことをするためにまずは自分で稼ごうと思ったら、すんなり銀行に受かってしまったんです。それが、卒業の半年前のこと。余裕ができたので、広報誌で見つけた劇団の「ヒロイン募集」の言葉につられて、「お手伝いだけでも…」と軽い気持ちで足を運びました。すると、なんと応募者はわたし一人(笑)。めでたくヒロインとなり(笑)、卒業までの半年という条件で親に認めてもらいました。

―そうですか!
実は、新社会人になってからもこっそり通って、ちゃっかり舞台に出てましたけれど。でも、仕事も忙しいうえ、夜は稽古をしたりして、体を壊してしまったんですね。それで結局、「芝居」を選びました。プロとして何とか食べていきたいという気持ちがあり、劇団「川」に5年いて、3年目の時に入団してきた西脇秀之ら歳の近いメンバーと、後に立ち上げたのが「劇団回帰線」です。
―当時、北海道でプロの俳優としてやっていくモデルみたいな方はいたのでしょうか。
あまりいませんでした。当時はネットもなかったし、最初は東京に行きたくて働き出したんですけれど。でも、「川」で、家庭を持ったり、社会人の傍ら、芝居を熱心に学ぶ方々に出会い、衝撃を受けたんです。まずは彼らのレベルまで頑張らないと…と思いました。そのうち、地元のタレント事務所を知り、ナレーションの仕事などもいただけるようになって、わざわざ東京に行かなくてもやれる道を作ればいいんだ、と思い直したんです。
―さまざまな作品にご出演されていますが、転機になったものをひとつ、選ぶとすれば。
98年のTPS作品「ブルーストッキングの女たち」。これは、83年に劇作家・宮本研が劇団「青年座」に書き下ろした代表作のひとつ。女権宣言を行い、婦人文芸雑誌「青鞜」に参加した平塚らいてうや神近市子ら大正期の実在の人物をめぐる群像劇です。東京の演出家・宮田慶子さんを招き、出演者をオーディションで公募したプロジェクトで、私は「伊藤野枝」役で主演の大役をいただきました。
―初めてギャラをいただいた外部出演とのことですが、いかがでしたか。
(演出の宮田さんは)厳しかったです。直前までイッセー尾形さんのワークショップに参加していて、演出の森田雄三さんにも言われたのですが、「何で型にはまるの?」と。
―「型」ですか。
それまで「川」と「回帰線」しか知らなかったので、芝居に柔軟性がなかったんですね。緊張もあって、自分のやっていることが全然見えていなかった。覚えているのが、宮田さんに言われた「このシーンで玄関を出る時、どちらの足から出てるの?」という言葉。左右が重要ではなく、「自分の演技に意識を持っているのか」ということ。を、言われているのだと、後で気づきました(笑)。その時はわからないから、「右から出なきゃいけないんだ!」と思って、意識して右から出ていましたけれど(笑)
―貴重な機会になりましたね。
「単語をひとつひとつ丁寧に立てて読む」など、セリフの読み方も勉強になりました。それは、いま講師を務める朗読講座にも役に立っています。あと驚いたのは、中学生の時に「面白いな」と切り取っていた雑誌の記事が、伊藤野枝の生涯を書いたものだったこと。稽古中に思い出して、不思議な感慨を覚えました。
―それはすごい偶然ですね! 運命というべきでしょうか。
着物の着方も必死に教わったし…30才の手前で、いろいろな「型」を崩してもらい、代わりに新しいものを与えていただいた舞台でした。苦しい現場でしたけれど、「年齢を重ねても、壊したり、壊されたりするんだ」と知り、人生の可能性を体感できたひとときでした。
―なるほど。スナックのママ役で、さまさまなご経験がにじみ出ているのが納得です。
(笑)嬉しいです。脳内だけ20代の新人で困ります(笑)。
―ほかにも、キノの中島さんが取り組む地元の中高生を巻き込んだ映画作りにも、キャストで参加されています。2012年の「僕らの興味期限切れの夏」には「八百屋のおかみさん」、2013年の「茜色クラリネット」には「市長秘書」役でした。現場のご感想は。

「僕らの興味期限切れの夏」

「茜色クラリネット」
若い子たちの頭と心の柔らかさ、スポンジのような吸収力は凄いですね。つい遊んじゃうこともありますけれど、スイッチが入った時の集中力ときたら! 高良さんではありませんが、彼らが現場でどんどん変化する様子を見ていると、若い頃に色んなものに触れるって素敵だなぁ、と。こうした取り組みに、また声を掛けてもらえるような「柔軟性」を自分も持ち続けていたいな、とも思います。
―2009年から3年間にわたり、人形劇師・沢則行さんを招いた人形劇のプロ養成プロジェクト「FAT!S」(フィギュア・アート・シアタ・札幌)も参加。2015年には、札幌の雪まつり会場で上演し、話題を呼んだ「雪の国のアリス」にも、人形操演で参加されました。
きっかけは、「回帰線」主宰の西脇から、「人形劇を勉強したらいい」と言われていたことです。その真意は、人形劇に必要な「見る・聞く・返す」などの基本的なスキルを改めて身に付けた方がよい、と捉えていました。若い頃はワークショップも多くなかったし、勢いだけの「発信」だったんですね。それで、良いチャンスだと思って飛び込みました。
―いかがでしたか。
実際に人形を操ると、動きに制限があるので、自分の思う「こういう感情のつもり」が、きちんと動かさないと伝わらないんです。喜怒哀楽、どんな仕草ならそう見えるのか。表現に対して客観的な視点を考える、良い機会になりました。その後、日本の古典芸能も学びたいと思い、今は人形浄瑠璃の勉強をして3年目になります。
―素晴らしいことですね! 雪まつり会場で見る「雪の国のアリス」にも圧倒されました。

沢さんがチェコで吸収してきた色彩や造形の感覚って、本当に凄いですよね。それを具現化するスタッフの方や、オペラを歌いあげたキャストの方々も尊敬します。お芝居の世界では出会えないような、違うジャンルのプロの方々とご一緒できて、本当にありがたい限りです。
―さまざまな表現に挑まれている小林さんの、理想の「役者像」とは。
「そこのみにて光輝く」を見て、「この女優さん誰だろう」と思ったら私だった、と驚いた知り合いがいたとお話しましたが、これが一番の理想。私って、超美人でも超個性的でも、体型が超スリムでも超ふくよかでもない。「器用貧乏」とも言われるように、極めているものはあまりないんです。でも、続けている「声」の表現、朗読やボイスワークをベースに、「え、あれがなるみさん?」と驚かれるような役者でいたい。〝七変化〟と言うと、格好良すぎるでしょうか(笑)

―長くお芝居を続けてきて、満足されたことは。
実は病気する直前、「もういいかな」と思った時がありました。バイトせず、お芝居だけで食べていけて、「あれ、もう夢叶っちゃったかなぁ」と。でも、「そこのみにて光輝く」で「スナックのママ」を演じた時、ありえない役をもらって、「まだまだあった!」と実感。考えてみると、地球上には70億人の人間がいて、その数だけ人生がある。私はまだまだ、そのうちの何十人かしか演じていないんですね。大げさですが、残り何十億人を演じられるように、常にフットワークを軽く、気持ちを柔らかくいられるような生き方をしたいですね。
―ありがとうございます。これからも応援しています!

小林 なるみ (Narumi Kobayashi)
俳優・ナレーター
劇団回帰線 所属(http://kaikisen.info/Top/KaikisenWeb/KaikisenWeb.html)
劇団での活動のほか 新国立劇場芸術監督でもある宮田 慶子氏や文学座の高瀬 久男氏、THE ガジラの鐘下辰男氏など 北海道内外問わず様々な演出家の作品に出演。
ラジオパーソナリティや札幌市中央図書館にてトランクカホンを使った朗読など声を使った表現も模索し続けている。
2005年から「Voice Work」朗読・発声講座を運営。北翔大学 非常勤講師。劇団ひまわり札幌養成所 講師。ヒューマンアカデミー非常勤講師。
主な出演作などは、ご本人のブログ「今日の風」(http://1aironaru.blogspot.jp/)をチェック!
新目 七恵(あらため ななえ)
1982年、北海道帯広市出身。十勝、函館の地域新聞記者を経て、2010年に札幌へ。“三度の飯より映画好き”の性格が高じて、現在、北海道をロケ地とした映像史料を収集・保存・公開するNPO法人「北の映像ミュージアム」に参加する傍ら、フリーのライターとして活動。2014年から朝日新聞北海道版でコラム「お気に入りの小さな旅」を連載中。
●北の映像ミュージアム http://kitanoeizou.net
(ほぼ日更新のスタッフブログ「北の映像ミュージアムの日々」を担当)
●お気に入りの小さな旅
http://www.asahi.com/area/hokkaido/articles/list0100132.html
本連載に関する感想・お問い合わせは nanae7ishiguro@yahoo.co.jp まで、お願いいたします。
















