TOP >> WEBコンテンツ >> 全国映画よもやま話 >> 浦河大黒座 上
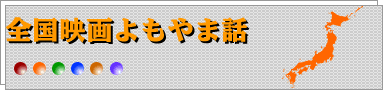
国内屈指の老舗映画館 大黒座の100年 上
2017年5月2日(火) 北海道新聞朝刊
斜陽の時代 家族で苦心
_高波の影響で運休が続くJR日高線沿線の日高管内浦河町。馬産地と漁業で知られる人口約1万3千人の町で唯一の映画館は、港からほど近い中心街の一角にある。映画ポスターの看板がなければ見落としおそうなたたずまい。それが来年9月1日、創業100年を迎える「大黒座」だ。
_4月2日の朝。来館者ゼロの日もある映画館は、久しぶりのにぎわいを見せていた。アニメ映画「この世界の片隅に」を見る人が、1回の上映に道内各地から20人以上訪れ、48席の半数近くが埋まる盛況だった。4代目館主の三上雅弘さん(65)は一人一人を見送った後に「いつもこれくらい入ったらいいね」と笑った。
押し寄せる客
_大黒座は、長く映画の盛衰を見てきた全国でも数少ない単館映画館の一つ。開館したのは米騒動があった1918年(大正7年)。雅弘さんの曽祖父辰蔵さんが、演芸小屋として芝居や浪曲などを上演したのが始まりだ。当時、座席は座敷、履物を預け、冬には貸し火鉢で暖を取ったという。
_辰蔵さんの死後、長女ヨネさんを経て雅弘さんの父政義さんが3代目を引き継いだ。時は映画全盛期の50年代。イカやサケ漁で栄えた漁師町には娯楽がなく、映画館の前には黒山の人だかりができた。
_雅弘さんの母雪子さん(91)は当時のことを記憶している。「波のように人が押し寄せ、映画館に入れない客もいた。お金は御用籠だけで収まらず、家中のタンスの棚を抜いて入れた」
_53年には、客席を220席まで増築し、入れないファンの需要に応えた。
副業で穴埋め
_娯楽の神様といわれた映画産業は60年代以降、斜陽の時代を迎える。テレビの普及により映画人口が減り、地方の映画館は姿を消していった。大黒座も例外ではなかった。
_客足が鈍り、暖房代がかさむ冬は、週末限定で上映する時期もあった。75年、雅弘さんが東京の大学を卒業して故郷に戻った時、映写技師、看板の描き手ら10人以上いた従業員は2人だけ。「昔の大黒座はそこにはなく、老け込んだ父親の姿にびっくりした」と映画館の手伝いを始めた。
_それでも経営は上向かず、父が始めた副業のクリーニングの仕事で赤字を穴埋めするのがやっと。94年には客席を220席から今の48席に減らした。
_年間1万人だった来館者は減る一方だが、1人でも入れば映画を流すこだわりは貫いた。父の他界後、4代目を引き継ぎ、幼いころから大黒座に通っていた妻の佳寿子さん(48)と母の3人で映画文化を守ってきた。そこに思わぬ難題が持ち上がった。
(浦河支局の斉藤徹が担当し、3回連載します)
















